2025年5月19日から21日まで台北で開催された、第11回アジア作物学会(ACSAC11)に参加してきた。台北にはコロナ禍のときに1ヶ月くらい滞在していたことがあり、主要な観光地はほぼ行き尽くしていたが、久しぶりにフィリピン以外の国に行けることとたくさんの日本人に会えるということで出発前から楽しみだった。桃園空港まではマニラから2時間ほど。かつて空港全体を包んでいた、感染対策と検疫による病院みたいな静けさは消え去り、ロビーには活気が戻っていた。聞こえてくる中国語や馴染みのある漢字で埋め尽くされた看板の数々に懐かしさと新鮮さが入り混じった感覚を覚えた。
学会前日
チェックインまで時間があったので、台北駅近くの国立台湾博物館で時間を潰した。この日はたまたま国際博物館の日で入館料が無料だった。雨が降っていたこともあり、入り口は雨宿り目的の人でごった返していた。ここの博物館は初めて訪れたが、台湾の歴史や自然についての展示が中心で上野の国立博物館の台湾バージョンといった感じだった。印象的だったのは日本の研究者についての展示物が多かったことだ。台湾は日清戦争から太平洋戦争の終わりまで日本が統治していたらしい。その時代に台湾に渡った日本人研究者による生物学や地質学、民俗学などでの地域研究への貢献が負の側面とともに中立的に紹介されていた。多くの国で他国に統治されていた歴史は、負の歴史として扱われ、その時代の研究資料などは破棄、黙殺されている。しかし台湾ではこうした成果を戦後の再建や開発にそのまま活かし現在まで発展してきた。歴史的背景と学術的な価値を切り離して活用してきた台湾の科学への姿勢は非凡なものであり、自分も研究者として見習わなければならない。そんなことを考えているうちに、チェックインの時間がやってきたので今回の宿(miniinn)に向かった。予約サイトで圧倒的な安さ(1泊2800円)かつ完璧な立地(台北駅まで徒歩30秒、学会会場まで徒歩5分)だったので、あまり確認せずに即決したが仕切りがカーテンのカプセルホテルだった。最初案内されたときはびっくりしたが、慣れればそこまで不便はなく共用の洗濯機などもあって良い施設だと思った。


ACSAC11
ACSAC11はシェラトングランド台北ホテルで開催された。高級ホテルが会場ということで料理などに期待していたが、想像以上だった。1日目は参加者全員が参加できる夕食だったが、カラスミやナマコなどの高級食材が目白押しだった。2日目の5000円の夕食では、こうした食事にアルコール飲み放題が付いており価格以上の満足感があった。今回の学会には台湾の農務省がスポンサーとして関与しており、全体として潤沢な予算が確保されていたようだ。
一方で、個人的には反省点が残る学会参加でもあった。第一に発表の練習不足である。正直発表前から練習不足なのはわかっていたが、まぁなんとかなるだろうと発表に臨んでしまった。当然なんとかなるわけもなく、グダグダな発表をした上に、台湾大学の学生からの質問でトドメを刺された。発表が終わった時には旅の恥はかき捨て!とか思っていたけれども、その日の夕食時に色んな人からフィリピンで研究しているの?と話しかけていただき、もっとましな発表をすれば良かったと死ぬほど後悔した。またホームステイ先の家族からは、Candaba(滞在先の地名)のこと色んな人に伝えてくれた?と連絡が来ていて胸が痛くなった。
第二に外国人との交流不足である。今回の学会は、日本人の研究者とも1年以上ぶりの再会だったため日本人中心に交流してしまった。話した外国人といえば、発表にトドメを指してくれた台湾大学の学生くらいである。せっかく台湾に来たのだからもっと新しい出会いを求めるべきだった。これは前回フィリピンの学会に参加したときも感じたが、東南アジアを舞台としたリモートセンシングの研究はまだまだ少ない。UAVなどの機械を持っていないというのもあると思うが、衛星画像やドローン画像を使ってどのようなことが解析できるのかということについてもあまり知られていないように感じる。つまり自分の発表を通してリモートセンシングの可能性を伝えたり、相手の研究に対してリモートセンシングならこんなことができるかもしれないと議論を持ちかけることは必ず新たな共同研究の種になるはずだ。将来海外の研究を続けたいと思っている以上、こうしたところはきちんとしないといけない。
と、反省点を挙げれば無限に出てくるが、1年以上ぶりに日本人研究者とたくさんお話しができたのはとても良い刺激だった。フィリピンにいると多くの人が朝は農作業、昼は昼寝、夜は飲み会というスローライフを満喫している。その中でモチベーションを保って研究を進めるのは至難の業だ。今回、学会で同期たちが着実に成果を挙げている姿を目の当たりにし、自分ももう一度気を引き締めて取り組もうと思った。

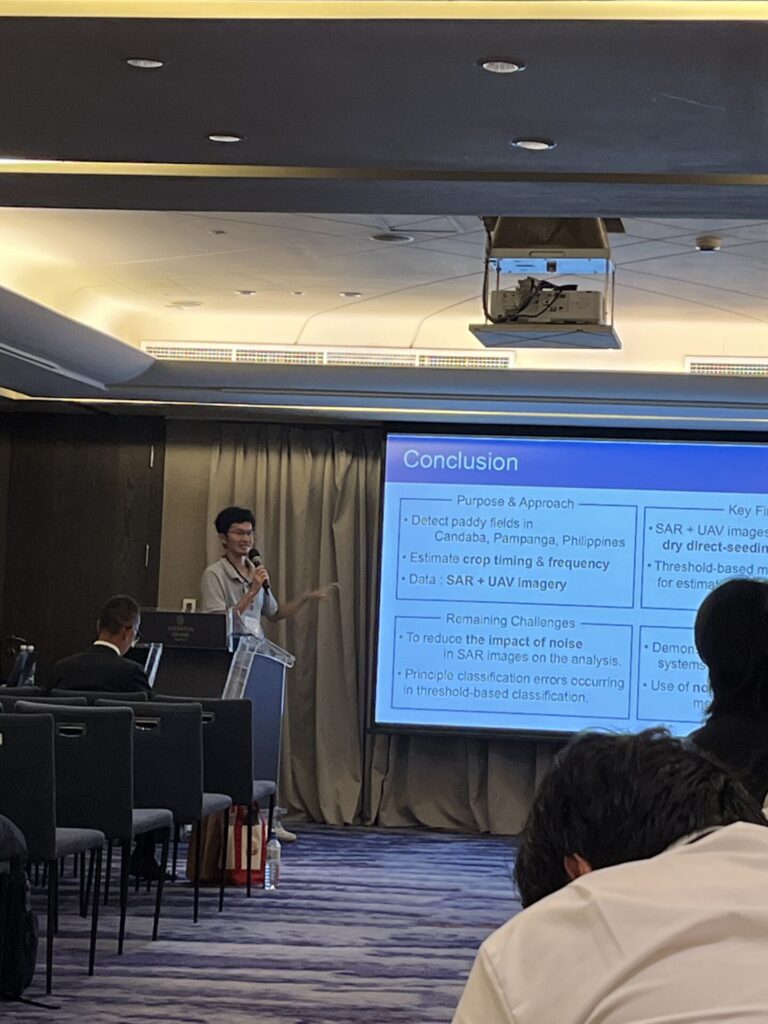
観光パート
海外学会の楽しみの一つといえば隙間時間での観光である。台湾は島国であるため珍しい固有種の鳥が多くバードウォッチングも楽しみの一つだった。特に前回の滞在で見れなかった「ヤマムスメ」が今回のメインターゲットだった。サークルの先輩やフィリピンで出会ったバードウォッチャー(今度記事にします)から台北植物園によくいると聞いていたので向かってみた。台北植物園は中正紀念堂から徒歩20分くらいの距離にあり都会のオアシスのような感じだったが、思ったよりたくさんの種類の鳥がいて楽しかった。カメラを持っているバードウォッチャーも何人かいて、台湾の鳥おじ(鳥を見ているおじさん)からヤイロチョウとズグロヤイロチョウの自慢話をされた。ヤイロチョウは日本だとウルトラレアの鳥(ズグロヤイロチョウは日本だと見れない)だが台湾では繁殖地で簡単に見れるらしい。超羨ましい。日本の探鳥地で、ベテランの鳥おじに今まで見た鳥を自慢されるのはよくあることだが、台湾でもあるのかと微笑ましい気持ちになった。無事「ヤマムスメ」も観察でき、ミッションは達成した。真ん中の写真のゴシキドリなどは、シェラトングランドホテルの目の前の木からも鳴き声が聞こえ、こういうカラフルな鳥が都会の中に普通に暮らしているのは東南アジアの魅力的なところだと感じた。



学会の日数に加えて1泊余分に旅程を組んでいたので最終日は1日観光を満喫した。午前中は、迪化街を散策した。訪れるのは初めてだったが、レンガ造りの街並みはどこかノスタルジックで、まるで別の国に迷い込んだような気分になった。ここには乾物屋さんや雑貨屋さんが軒を連ねていて、白キクラゲや燕の巣など日本だとなかなか見ないような食材がたくさん売られており見てるだけでも楽しかった。軒先ではちまきや豆花を売る屋台もあり、どれも魅力的でつい手が伸びそうになった。しかし朝に食べた爆弾おにぎりが予想以上にボリューム満点で、満腹だったため断念した。台湾には“軽食”という概念があまりないのか、どの屋台でもしっかり満腹になる量が出てくるのが面白い。
午後は、バスに乗って野柳地質公園に向かった。ところで、台湾の高速バスの運転手に怖いイメージを持っているのは僕だけなんだろうか。前回の滞在の時は高速道路で降車ボタンを押した客に対してすごい剣幕で怒っていたが、今回は高速道路走行中に席を立った子供に対して怒鳴り散らかしていた。まぁどちらも悪いのは客なんだが、もう少し優しく注意しても良いのになと思う。それともマニュアルに厳しく叱るように書いてあったりするんだろうか。野柳地質公園は、よく写真で見る奇岩がゴロゴロ並ぶ面白い公園だった。日本ではあんまり見れないような地形で、風化と侵食のパワーを感じられた。奇岩に触ったりするのは禁止だが、かなり近くまで近づくことができた。周りには倒壊している奇岩もたくさんあり、いつ崩れるのかはわからないのに安全面は大丈夫なのかと少し心配になった。奇岩エリアを抜けると半島の先まで散策路になっていた。散策路の看板には、よく見れる鳥として「ヤツガシラ」と「アカエリヒレアシシギ」(日本でも台湾でも超レア種、幻のポケモンみたいな感じ)が書いてあったが「シロガシラ」と「ハヤブサ」(まぁよくいる奴ら、シロガシラはポケモンでいうムックル)しかいなかった。こういう看板は過剰に期待させる傾向があるが、旅鳥を載せるのは盛りすぎだと思う。


エピローグ
観光も満喫し、フィリピンに帰る日がやってきた。マニラから滞在している農村まで距離があり移動に丸一日かかるため、朝早い便を予約していた。午前3時30分、台北駅のバスターミナルから桃園空港行きのバスに乗り込んだ。桃園空港行きのバスは24時間運行しておりとても便利である。帰りはchina airlineの飛行機だったが、値段は格安航空のレンジだったにも関わらず2時間のフライトで朝ごはんやドリンクのサービスがあり驚いた。フィリピンに到着すると、入国審査の前で制服姿のフィリピン人に入国管理局に連れて行かれた。なんでフィリピンに着いた瞬間からイベントが発生するんだと思っていると、半年以上の滞在が続いていて不法滞在の可能性があるから取り調べをするということだった。なんやかんや1時間くらい拘束されていたが、滞在理由やカウンタパートの先生について説明すると解放され入国できた。こういうゲリライベントに備えて、朝一の便で来て本当によかったと胸を撫で下ろした。マニラから滞在している農村までは2時間高速バスに乗ったあと1時間ジプニーという現地の乗合バスに乗る必要がある。高速バスはいつものように満員だったが、次の便がいつ来るかわからないので先人に習って地べたに座ってみた。今回の車掌さんは寛容な人で追い出されることなく、普通に券を切ってくれたので無事午前中にマニラを出ることができた。乗合バスでは、いつもの通り物乞いの子供たちがバスの天井に乗るパフォーマンスをしていた。多分すごいパフォーマンスなんだろうが車内からは一切その様子がわからないのが残念なところだ。帰ってきた当日から、あぁフィリピンに戻ってきたんだなと嫌でも実感させられたが、無事ホームステイ先に帰って来ることができた。次の国際学会でリベンジを果たすためにも、日本の学会で愉快な仲間たちと再会するためにもここでの調査を完遂させなければならない。調査期間もあと半年を切ったが、最後まで全力で取り組みたい。



コメント